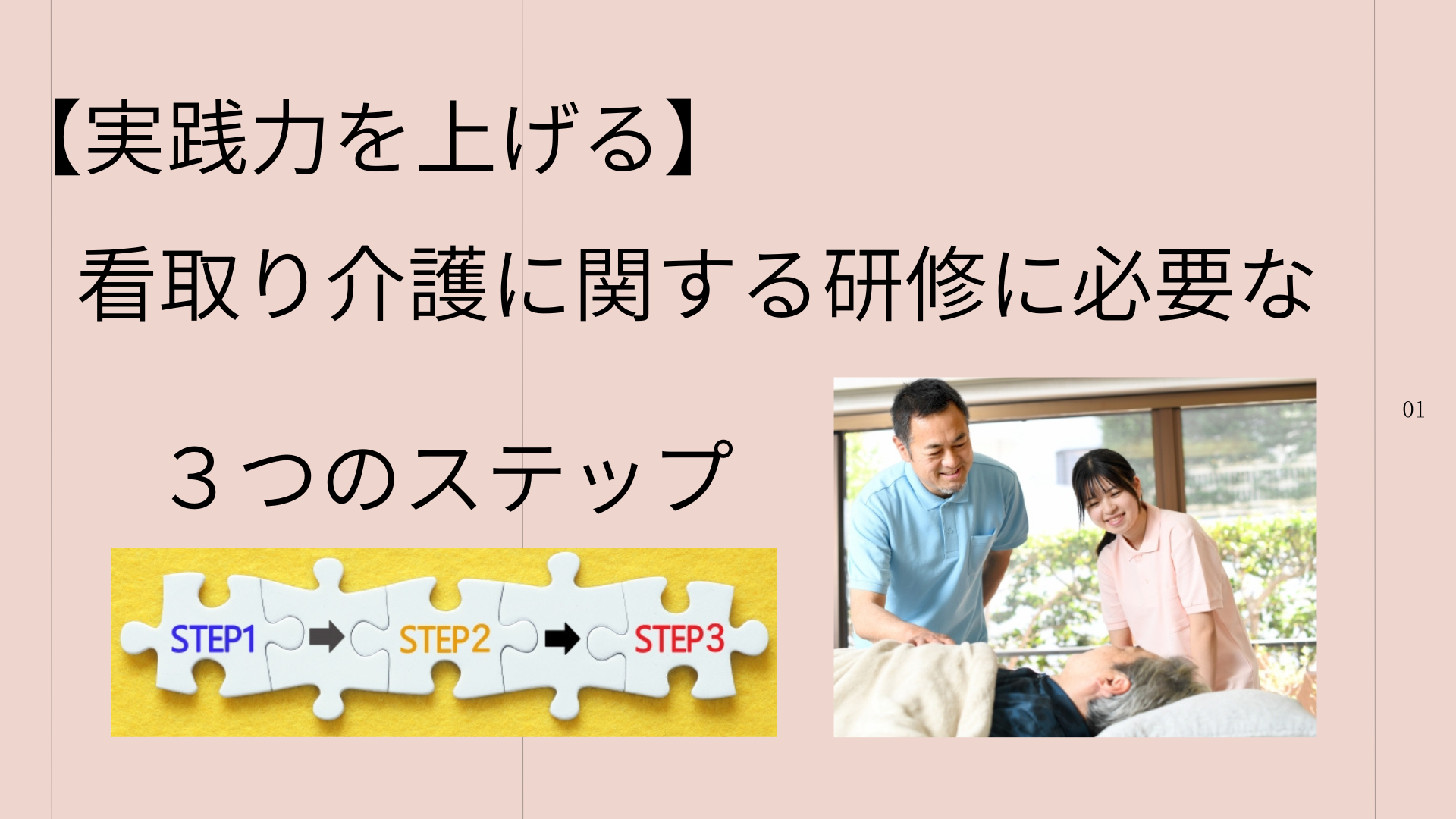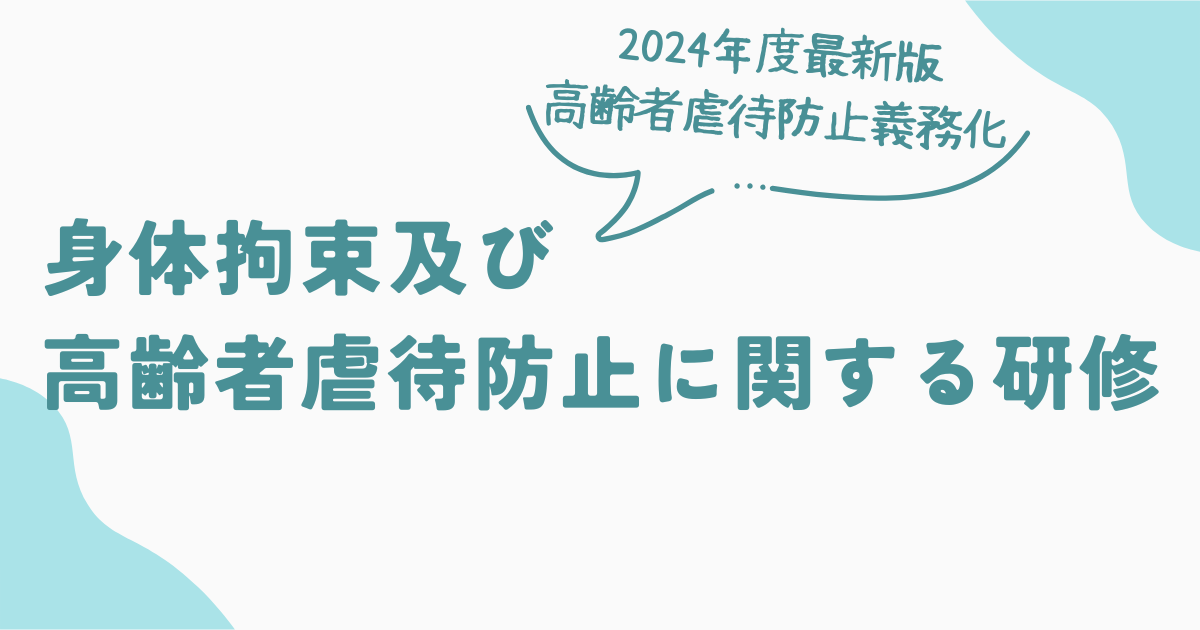「介護職の給与、全然上がらないよね。」
そんな会話を何度、職場で交わしてきたでしょうか。
処遇改善加算は入っている。給与は“上がっている”。
――でも、なぜか報われた気がしない。
そんなモヤモヤを抱えている現場職員、管理者、そして生活相談員のあなたへ。
この記事では、特別養護老人ホームの現場で働く生活相談員の私が、「なぜ介護職の給与は上がっても報われないのか」という疑問の本質に迫り、さらに、「この先どう変わればいいのか」という現実的かつ踏み込んだ提言を行います。
業界にとって耳が痛い話かもしれません。でも、変わらなければ守れないものがある。だからこそ、この記事を書きました。
介護職の給与は上がっているのに、格差が広がる現実
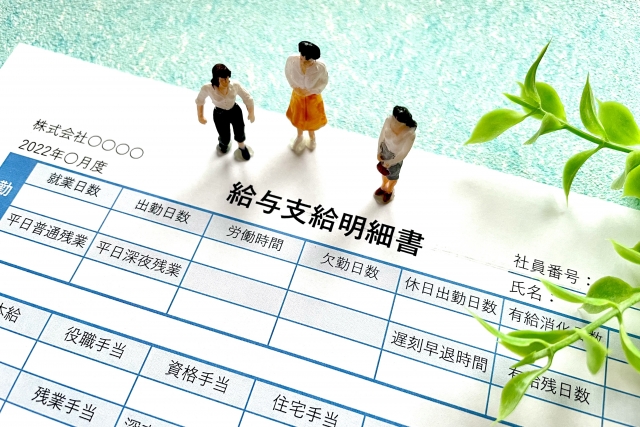
まず事実として押さえたいのは、介護職の給与が「上がっていない」わけではないということです。処遇改善加算などの制度で給与はじわじわと上昇しています。
しかし、それ以上のペースで全産業の給与が伸びているため、結果として格差が広がっているのです。
ポイント
- 介護職の平均年収:約400万円弱
- 全産業の平均年収:約500万円強
👉 その差は100万円以上。
これでは「介護の仕事を選びたい」と思ってもらうのは難しいのが現実です。
このまま“国頼み”では介護業界は立ち行かない──2つの根拠

1. 物価高による経営の圧迫
ガソリン代、光熱費、食材費がすべて高騰しています。
特に施設での食事提供や送迎に直結する部分は、現場の経営を直撃しています。
それでも介護報酬はほぼ据え置き。
現場で予算を見ている生活相談員の立場からしても、限界が見えてきています。
2. 覆せない現実:超少子高齢化
ポイント
- 日本は世界有数の高齢社会
- 介護保険の財源をこれ以上大きく増やすのは極めて困難
- 人口構造の未来予測は、ほぼ確実に当たる
つまり、国だけに頼る構造自体がすでに限界を迎えているのです。
保険外収入の改革こそが、生き残る道

なぜ食費や日用品費を据え置くのか?
私たちは家庭で、多少高くても米や野菜を「必要だから」買いますよね。
介護サービスも同じです。食費やおやつ代、日用品費などは生活に必要な支出です。
それなのに「値上げは悪」とされ、据え置きが常識になっていませんか?
「お金のない人を見捨てるのか?」
そういった声もあるでしょう。
でも、一つの施設が社会全体の福祉を背負うことはできません。
経営が立ち行かなくなれば、ご利用者も、職員も、その家族も守れなくなる。
生活相談員が本気で提言する、3つの変革策

1. 保険外サービス費の見直し
ポイント
- 食費や日用品費、送迎費など、実費負担の部分を現実に即して段階的に見直す
- その分を職員の処遇改善に還元する
👉 これは値上げではなく、「適正化」です。
2. 自費サービスの導入
外出支援、買い物代行、趣味活動支援など、ご家族の「+αのニーズ」に応えるサービスを有料で提供することで、事業の幅と収入源を広げられます。
3. 情報発信力の強化
今や、動画やSNSで「見える介護」「信頼される施設」を発信することが重要になっています。
私自身もYoutube「福祉の学び舎チャンネル」の運営や法人の広報、ホームページ作成、研修動画作成に携わっています。
✅ 介護業界にこそ、動画編集スキルは武器になる!
実は今、動画編集スキルを持つことで、施設のPR・採用活動・地域発信が一気に加速しています。
最短1ヶ月で動画編集スキルが身につく!【クリエイターズジャパン】

スキルを身につけて、あなたの施設やキャリアに「変化」を起こしましょう。
我慢の時代に、さよならを。
「福祉だから」「値上げはかわいそう」
そう言って現状維持を選ぶのは、ご利用者・職員・その家族の未来を諦めることに等しいと、私は思っています。
「強い者が生き残るのではない。変化できる者が生き残る」──ダーウィン
今こそ、現場から変革を起こす時。その一歩が、介護業界全体を変えるかもしれません。
最後に──特養の現場で奮闘する皆様へ
私は、特別養護老人ホームの生活相談員として、最前線でご利用者・ご家族の声を聴き、向き合ってきました。
だからこそ、経営、現場、人材、そして「生き残る福祉」のために声を上げたい。
我慢ではなく、変化を。福祉の灯を守るために、今こそアクションを起こしましょう。